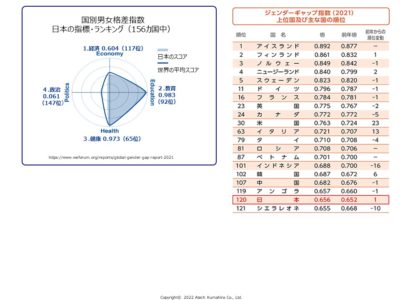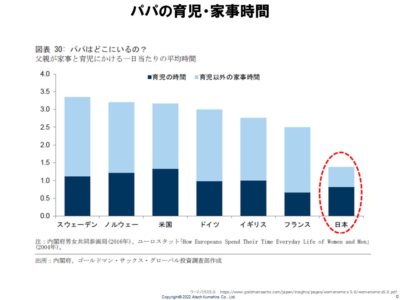トランスフォーメーショナル・ラーニング
文部科学教育通信2022.12.12掲載
20年以上も前に、アメリカの企業GEが取り組むリーダー養成プログラムについて学ぶ機会がありました。その際に、ラーニングには2種類あると教わりました。一つは、トランスフォーメーショナル・ラーニングで、もう一つは、トランザクショナル・ラーニングです。現在、リフレクションを広める活動をしていますが、そのきっかけとなった学習体験です。
トランザクショナル・ラーニングとは、知識やスキルを習得する学習のことで、私達が、一般的に学習という言葉でイメージする学びがこれに当たります。では、トランスフォーメーショナル・ラーニングとは、どのような学習なのでしょうか。
トランスフォーメーションと言う言葉は、性質や機能などが変化する際に使用します。例えば、デジタルトランスフォーメーション(DX)は、ITの浸透が、人々のあらゆる生活を良い方向に変化させることを意味します。トランスフォーメーショナル・ラーニングも同様に、学習者自身が変化する学習のことを言い、自己変容を伴う学習と説明されることもあります。
OECDが発表した学びの羅針盤2030では、それまで、キー・コンピテンシーと呼んでいた学習内容を、トランスフォーメーショナル・コンピテンシーと名付けました。従来の学校教育は、トランザクショナル・ラーニングが中心でしたが、トランスフォメーショナルという言葉が使われたことで、これからの時代の学校は、個人と社会をよい変化に向かわせる力を学ぶ場所であることが、この命名によって明確になりました。
コロナ禍での変化
コロナ禍で始まったリモートワークを事例に、2つのラーニングの違いについて説明してみたいと思います。コロナ禍で、突然、リモートワークが始まりました。その結果、「仕事は会社で行うもの」という常識が、「仕事は、会社でも家でも行える」という考え方に変化しました。そのために、新しいITシステムを活用する必要が生まれ、人々は、リモートワーク環境を整備するために、リモート会議や、オンラインで使うホワイトボード、チームとのコミュニケーションツールの使用方法を学びました。
リモートワークの事例では、「仕事は、会社でも家でも行える」というものの見方の転換がトランスフォーメーショナル・ラーニングです。5年前に、もし、誰かが上司に、「明日は、パソコンの前に座ってする作業が中心なので、自宅勤務にします」と上司に伝えたら、上司はどんな反応をしたでしょうか。コロナ禍では、社会全体の常識が変わりましたが、この際に一人ひとりが受け入れた常識の変化が、トランスフォーメーショナル・ラーニングです。同時に、人々は、リモートワークの環境を整えるために、新しいITシステムの使用方法を学びました。こちらが、トランザクショナル・ラーニングです。
リーダーのラーニング力
コロナは、社会全体に大きなインパクトを与え、私達の生き方や働き方にも大きな影響を及ぼしました。このため、私達は、主体的に自分の意思で、トランスフォーメーショナル・ラーンニングを行ったのではなく、危機を乗り越えるために行いました。しかし、20年前に、GEのリーダー養成プログラムで学んだことは、リーダーが自らの意思で、トランスフォーメーショナル・ラーニングを行うことで、会社の変革を成功させるという考え方です。前例を踏襲するのではなく、自分の意思で、新しい常識を自ら、そして集団で作り上げていくことがリーダーの使命であるというのが、GEのリーダー養成プログラムの教えでした。
学習する組織
リーダーのラーニングを支えたのは、学習する組織の技術の一つであるメンタルモデルという考え方でした。メンタルモデルとは、人が世の中や物事に対して持っている前提のことです。この前提は、経験を通して形成されます。メンタルモデルの教えでは、自分のものの見方が、どのような経験により形成したものの見方なのかに意識を向け、課題の要因を自分の外に探すのではなく、自分のものの見方を変えることに意識を向けるというものです。
リモートワークの事例であれば、5年前に、誰もが、仕事は会社で行うものと言う考え方をあたり前だと考えていた時に、自宅で働く仕事のスタイルを導入することを想像してみてください。管理職であれば、最初に頭に浮かぶのは、「家で怠けず仕事していることを、どうやって管理するのか」という問いかもしれません。あるいは、「チームでの仕事が進まない」という心配かもしれません。いずれにしても、たくさんの障害が頭に浮かび、「みんなが出社する方が、理にかなっている」という結論になるのではないでしょうか。
メンタルモデルの教えでは、この状態を俯瞰してみれば、実は、「障壁のすべての原因は、あなたのものの見方にあるのではないか」という問いを自分に投げかけます。管理しないと人は怠けるというものの見方が、家で仕事をする部下の勤務上状況が心配になる背景です。チームでの仕事が進まないというものの見方の前提は、例えば、物理的に一緒にいることがチームで仕事をする上で必須だという考えです。
トランスフォーメーショナル・ラーニングは、自らのものの見方を、自分の意思で変えることを意味します。先程の例では、コロナ禍で必要に迫られてリモートワークを導入するのではなく、必要に迫られた訳ではなく、自分たちが描く未来像となる働くスタイルを実現するために、リモートワークを始めるという世界です。当然、新しいことに取り組む際には、様々な障壁があります。ありたい姿を実現するために、その障壁を一つひとつクリアすればよい、これが、トランスフォメーショナル・コンピテンシーを持つ人の姿勢です。
アンラーン
リフレクションのひとつの型として、アンラーンを広める取り組みを進めています。アンラーンは、トランスフォーメーショナル・ラーニングの中でも、最も難易度が高い、過去の経験を通して形成されたものの見方(常識)を手放すことに焦点を置いた学習方法です。
アンラーンでは、自分のメンタルモデルをメタ認知することが、その基礎となります。自分が常識だと思っていることは、過去の経験により形成されたメンタルモデルであるという認識に立つことができれば、「これが正解だ」というものの見方を多面的、多角的に捉え直すことも可能になります。
アンラーンを成功させるためには、ありたい姿が何かを明確にする必要があります。そして、ありたい姿を実現する意思を持つことが前提になります。そのために何ができるのかと考えた時に至る結論が、アンラーンということになります。アンラーンは、誰にとっても、それほど簡単なものではありません。このため、ありたい姿を願う内発的動機を必要とします。アンラーンを成功させるために、ビジョンが必要なのはこのためです。
課題解決とトランスフォーメーショナル・ラーニング
トランスフォーメーショナル・ラーニングは、課題解決の手段のひとつです。課題山積の時代に生きる子どもたちが、未来を創造するためには、トランザクショナル・ラーニングの力を身につけただけでは十分ではなく、トランスフォーメーショナル・ラーニングの力と習慣を持つ必要があります。そのために、アンラーンを、まずは大人が習慣化することが大切であると考え活動しています。
皆さんも、ぜひ、身近なことからアンラーンにチャレンジしてみてください!