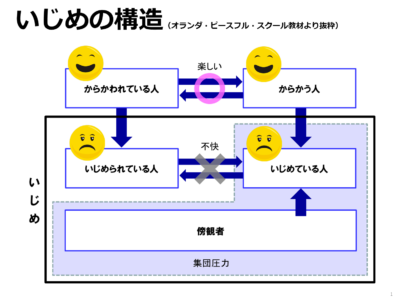学習する組織 ラーニング フォー オールの魅力(1)
文部科学教育通信 No.327 2013-11-11に掲載されたグローバル社会の教育の役割とあり方を探る(37)をご紹介します。
第37回より3回連続で、NPO法人ティーチ フォー ジャパンの学習支援事業であるラーニング フォー オール(旧称:寺子屋くらぶ)の魅力をお伝えしたいと思います。
私は、2010年のラーニング フォー オール(以下、LFA)の活動開始時から、研修や組織開発の面で継続的にサポートしています。LFAの組織としての成長を見守るとともに、常にLFAの運営に携わっている学生からも学んできました。今回は、これまでの活動を振り返りつつ、ラーニング フォー オールをご紹介する機会にしたいと思います。
シリーズ第1回は、LFAの概要をご紹介いたします。第2回では、LFAの独自の研修プログラムについて、第3回は、プログラム中の学習サイクルとプログラム後のリフレクションについてお伝えいたします。
ラーニング フォー オールについて
LFAは、学習支援を通して困難を抱える子ども達の可能性を広げるとともに、将来、教育現場や社会でリーダーシップを発揮する人材を育成する大学生向けのプログラムです。
団体のミッションは、次の3つです。
- 困難を抱えた子ども達の可能性を最大化する
- 参加した学生のリーダーとしての成長を実現する
- 卒業生による“社会全体で教育を変える”システムを創る
2010年夏より活動を開始し、今では関東・関西・東北・九州に拠点が広がっています。
2012年度までに、延べ1337人の子ども達に学習支援を行いました。プログラムに参加した学生教師は延べ445名、LFAのスタッフとして活動している人は述べ152名となっています。また、2013年は既に春季、夏季のプログラムが終了し、現在は秋季のプログラムが始まっています。
LFAの学習支援を受けた子どもの中には、学力的に高校への進学が厳しいと言われていたのに、学生教師がその子どもの躓いているところを一つずつ丁寧に指導し続けたことで、志望校に推薦合格した子どももいます。
LFAは学生が運営している組織です。採用や研修をデザインする際に、私のような社会人がアドバイスすることもありますが、組織を成長させ、子ども達により良い学習の機会を提供するために活動しているのは、情熱をもった学生たちです。
学習支援を持続可能な活動にするため、LFAは子ども達のおかれている状況に共感し、自ら学習し続けることのできる人材を仲間にしています。
学生教師とLFAスタッフの情熱や子ども達の変化を知ってもらうための説明会といった広報活動も、全て学生が行っています。説明会でのプレゼンテーションひとつを挙げても、初めてLFAに接した人々に彼らの思いが伝わるように、何度も練習し、フィードバックしあい、改善しています。
学生教師を採用する際にも、どのような思いを持っているのか、たとえ困難な状況に置かれても責任をもって子ども達を支援することができるのか、教師自身が学び続けることができるのかを確認するために、エントリーシートの提出や面接を実施しています。指導の経験やスキルだけでなく、子どもの目線で物事を考えることができるかどうかも重要な採用基準です。
LFAは、採用した学生に対して、指導を開始する前に20時間の事前研修、プログラムの期間中に20時間以上の中間研修を提供しています。また、指導期間中は教師に対して指導のフィードバックを行い、教師自身がPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Actサイクル)を回して、より良い指導ができるようにサポートします。プログラム終了後には「大リフレクション大会」という、活動を振り返って次の行動につなげる機会を設けています。このように、LFAは、子ども達の成長のために個人と組織の学習サイクルを綿密にデザインしています。
学習する組織としてのラーニング フォー オール
LFAの一貫した活動についてふれましたが、団体設立時からこのような流れがあったわけではありません。何度も試行錯誤を繰り返し、成功や失敗から学び続けた結果、現在のスタイルが確立されたのです。また、今でも常に子どもと教師にとってより価値のあるやり方を模索し続けています。
私はLFAを学習する組織であると考えています。LFAは、学習する組織の5つの規律を活動全体で体現しています。
学習する組織の5つの規律とは、以下の5点です。
|
①パーソナルマスタリー
②共有ビジョン
③メンタルモデル
④チーム学習
⑤システム思考 |
私は、LFAのスタッフや学生教師向けの研修を担当する際、学習する組織の話をしています。なぜこれら5つの規律が大切なのか、とLFAに携わる学生達が繰り返し考えることが、組織が成長していくための土壌づくりになると考えています。
LFAに参加している学生は皆、なぜLFAで活動するのか、どのような思いから参加しているのか、この先LFAでの経験を何に活かしたいのかといった①パーソナルマスタリーをもっています。個人の願いを叶える手段が、LFAでの活動である場合が多いのです。
また、LFAの活動を通して個人が成し遂げたいことと、団体のビジョンが一致しています。研修では、LFAのスタッフが団体のビジョンを学生教師に共有する機会がありますが、この②共有ビジョンと個人のビジョンをすり合わせることを目的としています。
LFAに携わる学生は、③メンタルモデルという色眼鏡が自らの学習を妨げる原因となることを理解しているので、自分とは異なる意見や価値観に出会った時、反発するのではなく、歩み寄ってそこから学ぼうとします。
また、個人がそれぞれPDCAサイクルを回して学習しますが、④チーム学習も盛んです。ナレッジと呼ばれる経験知をお互いに共有し、自分の指導に活かせるものは進んで取り入れることもできます。また、チーム全体で課題を解決することも行います。その際、ダイアログ(対話)という手法で、お互いの意見を尊重しながら、より良い答えを求めます。
学習支援に力を注いでいると部分的な課題にとらわれがちですが、⑤システム思考を用いて、全体を眺めた時にどこが問題なのか、どのような因果関係でその問題が起きているのかを捉え、アプローチします。
このように、子ども達の学習機会を最大化するために、LFAの学生教師やスタッフは、自ら学習し続けています。